かるかんとは?|鹿児島が誇る伝統の和菓子
かるかん(軽羹)は、鹿児島県を代表する伝統的な和菓子であり、ふんわりとした軽やかな食感と、自然な山芋の風味が特徴です。主な原材料は、すりおろした山芋、かるかん粉(うるち米を粗挽きした粉)、砂糖と極めてシンプルでありながら、蒸しあげることで素材の魅力を最大限に引き出した、上品な味わいに仕上がります。
蒸しあがったかるかんは、もっちり、しっとり、ふんわりとした口当たりが特徴で、「軽い羊羹」のような優しい甘さと食感から、その名が付いたとされています。見た目は控えめながら、地元鹿児島では格式ある和菓子として古くから親しまれており、贈答品や慶弔行事、お茶請けなど、さまざまな場面で楽しまれています。
かるかんには、主に2つの種類があります。一つは、四角い棒状のかたちをしたあんの入っていない「かるかん」。もう一つは、中にこし餡を包んだ「かるかん饅頭(まんじゅう)」です。後者は丸形や小判型の形をしており、見た目にも可愛らしく、現在では全国の百貨店や土産店でもよく見かける定番品となっています。


この伝統菓子が鹿児島の地で根付いた背景には、シラス台地が育む上質な山芋や、江戸時代に薩摩藩主・島津家が江戸から招いた菓子職人による創意工夫が大きく関わっています。鹿児島の風土と歴史が織りなすこの和菓子は、まさに郷土の誇りともいえる存在です。
さらに、1854年創業の老舗「明石屋」をはじめ、人気店「蒸氣屋(じょうきや)」などが、その味と技を今に伝えています。時代とともに抹茶味や桜風味などのアレンジも登場し、現代的なスイーツとしても進化を続けています。
かるかんは、鹿児島の風土・文化・素材が融合した、唯一無二の郷土和菓子です。その素朴な美しさと洗練された味わいは、観光客や和菓子好きにとって、まさに「知る人ぞ知る逸品」といえるでしょう。
かるかんの由来と名前の意味|なぜ「軽羹」と書くのか?
かるかん(軽羹)は、鹿児島県で生まれた伝統的な蒸し菓子であり、その名の由来には歴史と文化的背景が深く関わっています。ここでは、文献に見られる初出や「軽羹」という名称の意味について詳しくご紹介します。
薩摩で生まれた「軽羹」――その起源とは?
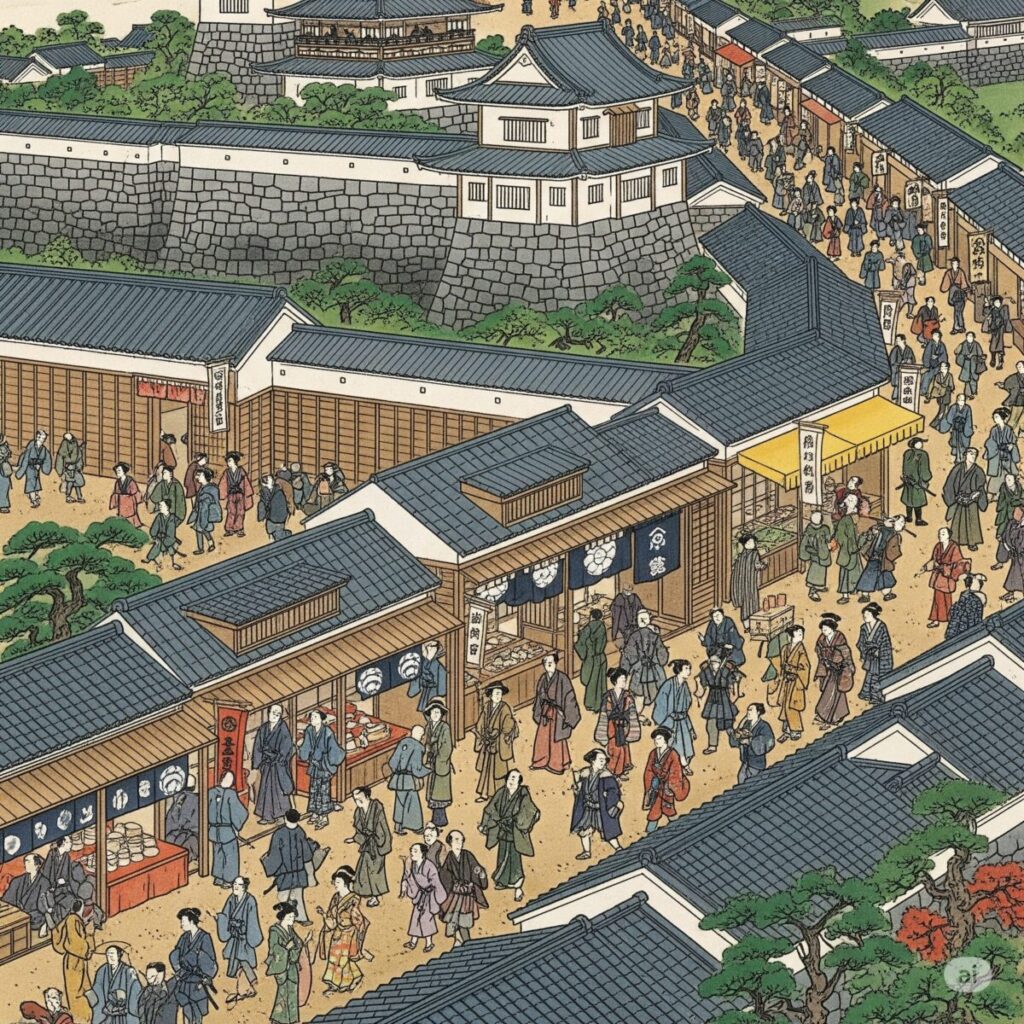
かるかんの歴史は古く、文献上での初出は元禄12年(1699年)とされています。この年の薩摩藩・島津家の献立記録「御献立留」に、“軽羹”という名が記されており、これが現在確認されている最も古い記録です。
当時のかるかんは、藩主の誕生日や祝宴など、特別な行事の際に供される高級な菓子であり、庶民が口にすることはほとんどありませんでした。こうした献上菓子としての背景が、かるかんに格式と伝統の重みを与えています。
その後、明治時代に入り、砂糖の流通と製菓技術の発展により、かるかんは徐々に庶民の間にも広まり、現在では鹿児島を代表する和菓子として広く親しまれるようになりました。
なぜ「軽羹」と書くのか? 名称に込められた意味
「かるかん」という名称の語源には諸説ありますが、最も有力とされているのが、「軽い羊羹(ようかん)」という意味から来ているという説です。
「羹(かん/あつもの)」という字は、もともとは中国語や古語において「汁物」「煮こごり」「とろみのある料理」を意味する言葉であり、日本ではこれが転じて、柔らかく蒸した食品や菓子にも用いられるようになりました。
一方、かるかんは蒸すことでふんわりと軽やかな食感に仕上がるのが特徴です。従来の羊羹のような練り物に比べて軽く、蒸しあがりがしっとりと柔らかいことから、「軽い羹(ようかん)」=「軽羹」という名称が生まれたと考えられています。
また一部では、「軽い羹(あつもの)」=軽い煮物という語義を転用した説や、原材料のシンプルさや仕上がりの軽快さから命名されたとする見方もあります。ただし、いずれの説も決定的な証拠はなく、正確な由来は今なお定かではありません。
郷土菓子に込められた意味と文化
かるかんの名前には、その食感や素材の性質を的確に表現するだけでなく、菓子文化が育まれてきた歴史的文脈が反映されています。江戸時代の薩摩藩で育まれたこの和菓子は、時代を越えて現代まで受け継がれ、鹿児島の誇る郷土文化の象徴として、今なお多くの人々に愛されています。
歴史と発祥|島津家と明石屋に見るかるかんのルーツ
かるかん(軽羹)は、鹿児島県で生まれた郷土和菓子であり、その歴史は江戸時代中期までさかのぼります。素材や製法の特徴だけでなく、藩主島津家との深い関わり、そして現代に続く和菓子文化の形成にまで至る、由緒ある背景をもった銘菓です。
江戸時代の献上菓子として始まった「かるかん」
かるかんが歴史の表舞台に登場するのは、元禄12年(1699年)。薩摩藩主・島津綱貴の誕生日の祝い膳として、「御献立留」という記録に「軽羹」の名が記されています。これは、現存する中で最も古いかるかんに関する記録とされており、鹿児島における菓子文化の始まりを象徴する資料でもあります。
当時のかるかんは、砂糖や山芋などの高価な材料を用いた贅沢な和菓子であり、藩主や上級武士、貴族階級のみが口にすることができる、献上用の格式高い菓子とされていました。庶民にとっては、憧れの存在だったといえるでしょう。
18世紀になると、かるかんの存在は鹿児島以外の地域でも文献に登場し始め、徐々にその名が広まっていきます。そして明治時代に入ると、砂糖が庶民にも手に入るようになり、かるかんは次第に高級菓子から日常の和菓子へと変化していきました。こうして、鹿児島を代表する銘菓として定着していったのです。
発祥の地・鹿児島と名店「明石屋」の登場
かるかんが鹿児島で誕生した背景には、地理的・気候的な条件が大きく影響しています。鹿児島はシラス台地と呼ばれる火山灰由来の土壌が広がっており、この土地は山芋の栽培に非常に適していました。良質な山芋をふんだんに使える環境が、かるかんのような蒸し菓子の発展を後押ししたといえます。
また、かるかんの普及に重要な役割を果たしたのが、播州明石出身の菓子職人・八島六兵衛です。彼は、島津藩主・島津斉彬に招かれて鹿児島に渡り、1854年に和菓子店「明石屋」を創業。現在も続くこの老舗は、かるかん元祖の店として知られており、当時の技法を守りながら、伝統の味を現代に伝え続けています。
八島六兵衛のように、島津家が積極的に外部からの技術者を招いた背景には、斉彬の技術奨励策や殖産興業への関心がありました。彼の進取の気風が、鹿児島に独自の和菓子文化を育む一因となったのです。
郷土菓子としての「かるかん」の定着
こうした歴史的経緯を経て、かるかんは鹿児島の自然・人・文化が融合して生まれた郷土の味として定着していきます。明治以降には、冠婚葬祭やお茶席の定番菓子として地域に根付き、今では県外からの観光客にも広く知られるようになりました。
近年では、明石屋の他にも「蒸氣屋」などの名店が登場し、それぞれに独自の工夫を加えながら、伝統と革新を融合させたかるかんづくりが続けられています。
かるかん饅頭とは?|中に餡が入った定番の銘菓
かるかん饅頭(まんじゅう)は、鹿児島県をはじめ九州地方で広く親しまれている郷土の銘菓で、ふわふわ・もっちりとしたかるかん生地の中に、上品な甘さの餡を包んだ蒸し菓子です。素材の自然な風味を活かし、和菓子らしい繊細な口当たりと素朴な味わいが特徴となっています。
ふわもち食感と上品な甘さが魅力
かるかん饅頭の最大の魅力は、なんといってもその食感と香りです。生地には山芋(自然薯)と米粉、砂糖が使用されており、粘りとふんわり感をあわせ持つ独特の仕上がりになります。白くてなめらかな外皮は、噛むほどに山芋の自然な甘みが感じられ、中に包まれたこし餡とのバランスが絶妙です。
餡には、一般的に甘さ控えめのこし餡が使われることが多く、素材の風味を引き立てるように設計されています。一口ごとに感じるしっとり感と優しい甘さは、現代の嗜好にも合い、老若男女に親しまれています。
見た目はころんとした丸い形が一般的ですが、小判型や楕円型のものもあり、店によって個性が見られます。近年では、栗餡や柚子餡などの季節限定商品も登場し、バリエーションも豊かになっています。
かるかん饅頭の成り立ちと進化
本来の「かるかん」は、餡を入れずに四角い棹状に固めた蒸し菓子でした。これに餡を包んだ饅頭型の「かるかん饅頭」が一般化したのは近代以降とされており、山芋と米粉の生地に餡を合わせるという発想が生んだ進化形の和菓子です。
かるかん文化が発展した背景には、薩摩藩主・島津斉彬が保存食や贈答品としての菓子文化を重視し、菓子職人の登用を積極的に進めたことも大きな要因となっています。明石屋や蒸氣屋などの老舗和菓子店が、その伝統を今に受け継いでいます。
食べ方と親しまれ方
かるかん饅頭は、そのやさしい甘さと食べやすさから、お茶請けや日常のおやつとして親しまれているほか、贈答用や鹿児島土産の定番としても高い人気を誇ります。しっかりと包装されており、日持ちもするため、遠方へのおみやげとしても重宝されています。
また、冷やして食べても美味しく、餡と生地の一体感が増すことから、夏場には冷蔵庫で冷やしてから楽しむ方も少なくありません。
素材へのこだわりと地域性
使用される素材は、鹿児島県内でとれる良質な山芋をはじめ、地元産の米粉を用いたものも多く、地域の風土に根差した製法が守られています。伝統的な製法にこだわる老舗のほか、現代的なアレンジを加えた新進和菓子店も登場しており、幅広い層に受け入れられています。
作り方とレシピの基本|家庭でも作れる?
かるかんは、鹿児島県で生まれた伝統的な和菓子ですが、材料と道具さえそろえば家庭でも比較的簡単に作ることができる蒸し菓子です。特に「かるかん饅頭」は、ふんわり軽い山芋生地と、甘さ控えめの餡の調和が楽しめる人気の一品。ここでは、基本的な材料と作り方、成功のコツをご紹介します。
基本の材料(かるかん饅頭 約18~20個分)
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| かるかん粉(または上新粉) | 300g |
| 長芋(すりおろし) | 300g |
| 砂糖 | 240g |
| 水 | 150〜180cc(調整可) |
| 卵白 | 2個分 |
| こし餡(中に詰める) | 約300g |
※「かるかん粉」は、うるち米を水洗い・乾燥し粗く挽いた粉で、市販でも入手可能。上新粉での代用も可能です。
作り方の流れとコツ
- 長芋の下処理
長芋は皮をむいてすりおろし、変色防止のために酢水に数分間浸けておくと色が美しく仕上がります。 - 砂糖を加えて混ぜる
すりおろした長芋に砂糖を数回に分けて加え、そのつどしっかりと混ぜます。粘りが出るまで丁寧に混ぜるのがポイントです。 - 水を加えて調整
長芋の水分量に応じて水を少しずつ加え、生地のなめらかさを調整します。混ぜすぎると粘りがなくなるため注意しましょう。 - 粉を加えて混ぜる
かるかん粉(または上新粉)を加え、さっくりとボウルの底から持ち上げるように混ぜます。粘りを活かすため、練りすぎには注意します。 - 卵白を泡立てて加える
卵白を角が立つまでしっかり泡立て、メレンゲ状にします。2~3回に分けて生地に加え、泡を潰さないように優しく混ぜます。ふっくら仕上げの鍵となる工程です。 - 型に流し入れ、餡を包む
耐熱性の型(湯呑・プリン型などでも代用可)に油を薄く塗り、生地を半量流し入れた後、丸めたこし餡を中央に置き、残りの生地で覆います。 - 蒸し器で蒸し上げる
蒸気の立った蒸し器で12〜20分ほど、中火~強火で蒸します。竹串を刺して生地がついてこなければ完成です。
アレンジ・時短レシピも可能
少量で試したい場合や手軽に楽しみたい方には、以下のような簡単レシピ(5人分)もおすすめです。
- 長芋すりおろし:90g
- 砂糖:75g
- かるかん粉:75g
- 水:60cc
これらを順番に混ぜて型に流し、蒸し器で約15分蒸せば完成。餡を入れずに棒状や丸型に成形すれば、昔ながらの「かるかん」スタイルでも楽しめます。
作る際のワンポイント
- 卵白を使うことでふんわり感がアップしますが、省略しても山芋の粘性で十分ふっくらと仕上がります。
- 型がない場合は、湯呑やマフィン型、シリコンカップでも代用可能です。
- 生地が硬すぎる場合は水を少量ずつ加えて調整しましょう。
かるかんの文化的役割|鹿児島の冠婚葬祭と贈答文化
かるかん(軽羹)は、鹿児島県で古くから親しまれてきた伝統和菓子であると同時に、地域の儀礼や人間関係を結ぶ文化的な意味合いを持つ菓子でもあります。単なる食べ物を超えて、人と人とのつながりを表現する象徴的な存在として、冠婚葬祭や贈答の場で幅広く用いられてきました。
冠婚葬祭におけるかるかんの役割
かるかんは、江戸時代には薩摩藩主・島津家の特別な献上菓子として用いられており、元禄12年(1699年)の献立表にその記録が残されています。このように、もともとは武家社会の格式高い祝いの菓子として生まれました。
時代が下るにつれて、かるかんは庶民にも広がり、現在では以下のような人生の節目の儀礼に欠かせない和菓子として重宝されています。
- 結婚式・婚礼引き出物
- 出産祝いや初節句
- 入学・卒業祝い
- 葬儀・法事などの供物や引き菓子
白くふっくらとした見た目や、自然素材で作られることから、清浄・純粋・誠実といった縁起の良さが感じられ、人生の大切な場面にふさわしい品とされています。鹿児島では、こうした式典や集まりの場で必ずといっていいほど登場する定番和菓子となっています。
贈答文化に根ざした郷土の銘菓
かるかんは、冠婚葬祭だけでなく、贈答文化においても非常に重要な位置を占める菓子です。お中元・お歳暮・年末年始の挨拶、帰省時の手土産、企業の訪問時の菓子折りなど、さまざまなシーンで用いられています。
特に鹿児島県民にとっては、「派手さ」や「豪華さ」よりも、「素朴さ」や「誠実さ」「気持ちを伝えること」が大切にされており、かるかんはそうした価値観を体現する贈り物として重宝されてきました。
また、蒸し菓子であるため比較的日持ちがすること、サイズや包装のアレンジがしやすいことも、贈答用としての魅力を高めています。
文化的意義と地域に根ざした和菓子
以下のように、かるかんは鹿児島の暮らしの中に深く根付き、地域文化の一部として受け継がれている和菓子です。
| 文化的な役割 | 具体的な場面 |
|---|---|
| 冠婚葬祭の引き菓子 | 結婚式、法事、葬儀、初節句など |
| 贈答・手土産 | 季節のご挨拶、年末年始、お中元・お歳暮など |
| 日常の団らん | 家族の集まり、茶の湯、おやつとして |
かるかんは、鹿児島の人々の人生儀礼と人間関係を結ぶ「心の和菓子」とも言える存在です。祝いの場にも、弔いの場にもそっと寄り添い、相手を思う気持ちを静かに伝える役割を果たしています。
持ち帰り・賞味期限・保存方法の目安
かるかんやかるかん饅頭は、贈答品やお土産として高い人気を誇る和菓子ですが、その繊細な風味を損なわずに楽しむためには、保存方法や賞味期限の目安を知っておくことが大切です。ここでは、購入後の持ち帰り方法から保存のコツまで、実用的なポイントをまとめます。
持ち帰り時の注意点
かるかんは基本的に常温で持ち運び可能な和菓子ですが、以下の点に気をつけるとより安心です。
- 直射日光を避け、涼しく風通しの良い環境で持ち歩きましょう。
- 夏場や高温多湿の時期には、保冷バッグなどを使用するのがおすすめです。
- 長時間の移動や郵送の際も、梱包状態を確認し、極端な高温にならないよう注意してください。
賞味期限の目安
| 種類 | 賞味期限の目安(未開封・常温) |
|---|---|
| かるかん | 約8~14日 |
| かるかん饅頭 | 約7~11日 |
| 冷凍保存した場合 | 約2週間~1ヶ月 |
賞味期限は製造日や保存状態によって異なるため、商品ごとの表示を必ず確認してください。また、開封後は劣化が早いため、冷蔵保存のうえ1~2日以内に食べるのが基本です。
保存方法とおいしく保つコツ
未開封時(常温)
- 保存場所は15~25℃程度の冷暗所が適しています。
- 高温多湿・直射日光は避けるようにしましょう。
- 保存料不使用の製品が多く、賞味期限を過ぎると風味が大きく損なわれるため、早めの消費がおすすめです。
開封後(冷蔵保存)
- ラップや密閉容器に入れて冷蔵庫で保存します。
- 冷蔵すると生地が硬くなりがちですが、食べる前に霧吹きで湿らせてラップをかけ、電子レンジで20~30秒加熱するか、蒸し直すとふんわり感が戻ります。
- 保存は基本的に2日以内が目安です。
冷凍保存
- 多めに購入した際などは冷凍保存も可能です。
- 冷凍時は密閉袋に入れて空気を抜くと、乾燥や風味の劣化を防げます。
- 解凍は冷蔵庫での自然解凍がおすすめ。食べる直前に軽く温めることで、蒸したてのような食感を再現できます。
食べるときの注意点
- カビ、糸引き、変色、異臭、酸味がある場合は食べずに処分してください。
- 保存料を使っていない製品が多いため、特に夏場や湿度の高い時期は注意が必要です。
かるかんは繊細な風味と食感が魅力の和菓子です。正しい保存と食べ方を知ることで、いつでも美味しく楽しむことができます。お土産や贈り物として購入する際も、保存方法を伝えるとより喜ばれるでしょう。
鹿児島の名店紹介|明石屋・蒸気屋の魅力と違い
かるかんといえば、鹿児島を代表する和菓子として知られていますが、その魅力を今に伝える老舗・人気店として欠かせないのが「明石屋(あかしや)」と「蒸気屋(じょうきや)」です。いずれも県内外に多くのファンを持ち、贈答用やお土産として高い評価を受けています。
ここでは、それぞれの店の特徴やこだわり、味の違いについてご紹介します。
元祖の風格と職人の技|明石屋(あかしや)
「明石屋」は、江戸時代に薩摩藩主の命を受けて招かれた播州明石出身の菓子職人・八島六兵衛によって創業された、かるかん発祥の老舗和菓子店です。現在も7代目が伝統の味を守り続けています。
- 使用する素材はすべて地元鹿児島産にこだわり、特に自然薯の質には定評があります。
- 生地はねっとり・しっとりとした食感で、口の中に広がる自然薯の風味と上品な甘さが絶妙なバランスを生み出します。
- 餡には北海道産小豆を使用し、ずっしりとした重厚感とコクのある甘さが楽しめます。
- 高品質ゆえに価格はやや高めですが、贈答用や格式ある場にふさわしい和菓子として高い評価を得ています。
- 鹿児島市内に多数の直営店があり、空港・駅・オンラインショップでも購入可能です。
手軽さと親しみやすさが魅力|蒸気屋(薩摩蒸気屋)
「蒸気屋」は、比較的新しいブランドながら、看板商品の「かすたどん」とともに県内外で知名度を高めた、現代的でカジュアルな和菓子店です。かるかんも看板商品のひとつとして人気を集めています。
- 明石屋と比べると、生地はやや粗めで軽やかな口当たりが特徴で、もっちりとした食感を好む層に好まれています。
- 餡は控えめな量で、全体的にさっぱりとした甘さが魅力です。
- 価格は1個100円台とリーズナブルで、土産品として手に取りやすい価格帯。
- 鹿児島市を中心に空港や駅、土産店に広く展開しており、手軽に購入できるのも魅力のひとつです。
- 「かるかん」と「かすたどん」のセットなどもあり、観光客にも人気です。
明石屋と蒸気屋の比較表
| 項目 | 明石屋 | 蒸気屋(薩摩蒸気屋) |
|---|---|---|
| 創業 | 江戸時代・かるかん発祥の老舗 | 昭和以降・比較的新しいブランド |
| 生地の特徴 | ねっとり・しっとり・きめ細かい | もちもち・やや粗め・軽い食感 |
| 餡の特徴 | 北海道小豆使用・重厚な甘み | 控えめな量・あっさりした甘さ |
| 原材料 | 自然薯・米粉・砂糖 | 山芋・米粉・砂糖・麦芽糖など |
| 価格帯 | 約170円/個(高級志向) | 約108円/個(手頃価格) |
| ターゲット層 | 本格派・贈答用・伝統を重視する方 | 観光客・若年層・手軽に楽しみたい方 |
| 店舗展開 | 鹿児島県内14店舗以上、空港・駅・通販対応 | 各地に展開・土産店・空港・駅・通販でも購入可能 |
どちらも魅力的な鹿児島の味
- 明石屋は、伝統と格式、素材と技にこだわる老舗の味。かるかんの原点を味わいたい方に最適です。
- 蒸気屋は、親しみやすく手に取りやすい価格と味で、カジュアルな贈り物や自分用におすすめです。
いずれの店舗も鹿児島空港や駅構内で購入可能なため、観光や帰省の際には食べ比べて味の違いを楽しむのも、郷土菓子の奥深さを体感する良い機会になります。
まとめ|郷土の味「かるかん」を今に伝える
かるかん(軽羹)は、鹿児島県を代表する郷土菓子として、長い歴史とともに育まれてきた蒸し菓子です。素材はシンプルでありながら、山芋の香り・米粉のやさしさ・蒸しの技が一体となった、素朴でありながら奥深い味わいが魅力です。
そのはじまりは、元禄12年(1699年)、薩摩藩の島津家における祝いの献立からでした。武家の献上菓子として生まれたかるかんは、江戸後期から明治にかけて庶民にも広まり、冠婚葬祭や贈答文化のなかで地元に深く根づいていきました。
今日では、「かるかん饅頭」として餡を包んだものが一般的に知られ、鹿児島空港や観光地の土産としても人気です。明石屋のような老舗から蒸気屋のような新興店まで、伝統と革新が共存する形で現代のかるかん文化が続いています。
さらに、家庭で作ることもできる素朴さや、冷凍保存が可能な利便性もあり、地域内外の多くの人々に親しまれています。
かるかんは単なる和菓子ではなく、鹿児島の自然・歴史・人々の思いが詰まった「文化のかたち」そのものです。祝いの場にも、別れの場にも、日常のひとときにも寄り添うかるかん。その味わいを通じて、郷土の心にふれる体験ができることでしょう。
参考文献一覧
- 和菓子の魅力 – かるかんとは?(https://wagashimiryoku.com/wagashi/karukan/)
- 明石屋公式サイト・お客様Q&A(https://www.akashiya.co.jp/customer/qa_12.html)
- 農林水産省 – 郷土料理検索(かるかん)(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/karukan_kagoshima.html)
- Wikipedia – 軽羹(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%BE%B9
- Tabiiro – 旅色特集「鹿児島の銘菓・かるかん」(https://tabiiro.jp/kankou/article/karukan-kagoshima/)
- 西原商会 – 鹿児島銘菓の歴史紹介(https://www.nishihara-shokai.shop/blog/goods/kagoshima_meika)
- 備蓄倶楽部 – 【鹿児島銘菓】明石屋の軽羹(かるかん)は自然薯で勝負する!(https://akitushima.com/akashiya-karukan/)
- YouTube – かるかんの作り方動画(https://www.youtube.com/watch?v=HlfrV9mK9Ig)
- レシピサイトTenon – かるかんの作り方(https://tenon.site/2020/05/08/karukan/)
- JAかれんレシピ – かるかんまんじゅう(https://karen-ja.or.jp/recipe/post-9.html)
- TOMIZレシピ – かるかん饅頭(https://tomiz.com/recipe/pro/detail/20221219003218)
- 薩摩蒸気屋(蒸気屋)公式 – 商品紹介ページ(https://jokiya.com/item-list?categoryId=38176)
- 明石屋公式ストーリー・かるかんの由来(https://www.akashiya.co.jp/stories/003.html)
- Yahoo!知恵袋 – かるかん保存に関するQ&A(https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340624283)
- せん花園オンラインショップ(https://senkaen-shop.com/?pid=181078556)
- お菓子工房くめんや – 保存・解凍方法(https://kumenya.co.jp)
- トリップアドバイザー掲示板 – 蒸気屋や明石屋の土産事情(https://www.tripadvisor.jp/ShowTopic-g298211-i10768-k8581822)
- Mie i Sogniブログ – 明石屋のかるかんレビュー(https://mieisogni.exblog.jp/21553082/)

コメント