- 鯖飯とは?――定義と名称の多義性
- 由来・歴史 – 保存食と「鯖街道」が育んだ文化
- 地域バリエーション – 和歌山の炊き込み、都市部の丼、福岡の「ごま鯖」
- 鯖飯の特徴 – 素材・味つけ・調理法(炊き込み/混ぜご飯/丼・出汁茶漬け)
- 基本レシピ(炊飯器・土鍋)と簡単レシピ(混ぜるだけ・缶詰活用)
- 食べ方と献立例――汁物・副菜の組み合わせ/お茶漬けアレンジ
- 現代の展開――専門店文化(東京・大阪・荻窪)とテイクアウト
- コンビニ・通販・お土産――身近に広がる鯖飯
- 保存・弁当術――冷凍・持ち運びのコツ
- 英語で紹介する鯖飯(Mackerel Rice / Rice cooked with mackerel)
- 参考文献・参照資料
鯖飯とは?――定義と名称の多義性
「鯖飯(さばめし)」は、鯖と米を組み合わせた飯料理の総称です。古典的な代表例は和歌山県・那賀地方に伝わる郷土料理で、塩鯖と醤油で素朴に炊き上げる炊き込みご飯。もともとは山間部で客をもてなす際のごちそうとして作られ、現代では生鯖に香味野菜(ごぼう・生姜・椎茸・青ねぎ等)を合わせるアレンジも広がっています。
広い意味では、鯖飯は炊き込み(米と鯖を一緒に炊く)、混ぜご飯(炊き上がりの飯に焼き鯖などを混ぜる)、丼・出汁茶漬け(白飯に焼き鯖を載せ、そのまま/薬味/出汁で楽しむ)といった複数のスタイルを含みます。
一方で、鯖と米という共通点を持ちながら、塩・酢で〆た鯖を飯と合わせる保存寿司(さばずし/きずし)は寿司文化の系譜に属し、鯖飯とは目的・調理アプローチが異なる別カテゴリーとして扱われます。
なお「サバメシ」という語は、文脈によっては「サバイバル飯(被災時などの即席調理)」の略称としても広く用いられ、鯖料理を指さない場合があります。本記事では混同を避けるため、“鯖×米の飯料理”としての「鯖飯」を主題とします。
由来・歴史 – 保存食と「鯖街道」が育んだ文化
鯖飯の古層には、海から遠い山間部での“塩干物文化”があります。和歌山県・那賀地方では新鮮な魚が得にくい環境から塩鯖が貴重なタンパク源となり、祭礼や季節の集まりで客をもてなすごちそうとして、米に塩鯖と醤油だけを合わせて炊く素朴な鯖飯が受け継がれてきました。現代になると、生鯖にごぼう・生姜・椎茸などの香味野菜を合わせて炊くレシピも普及し、時代に応じて味わいが更新されています。
もう一つの大きな流れが、若狭(福井)から京(京都)へ続く「鯖街道」です。若狭は古来「御食国(みけつくに)」として都に食材を供給し、鯖は塩漬けにして約2〜3日の行程で京都へ運ばれました。道中で塩がほどよく回り、到着時には食べ頃に整う――この保存と輸送の知恵が、都の食文化を支え、のちの「さばずし」など保存寿司文化の基盤にもなりました。
こうして「鯖×米」の結びつきは、保存技術と流通網に支えられた寿司系(さばずし・きずし等)と、家庭や郷土で発達した非寿司系(炊き込み・混ぜご飯・丼)という二つの系譜に枝分かれしました。目的(保存/炊き立て)や調理アプローチが異なるため、同じ素材でも別の文化圏として位置づけられます。 また近代以降の流通の発達は生鯖を使う炊き込みの広がりを後押しし、地域の“ごちそう飯”から、日常のごはんへと裾野が広がっていきました。
要点
・山間部では塩鯖×醤油の保存食的な炊き込みが“おもてなし”として定着。
・鯖街道が塩鯖の都への供給を支え、保存寿司文化の基盤に。
・近代以降は生鯖+香味野菜などへ進化し、非寿司系の鯖飯が多様化。
地域バリエーション – 和歌山の炊き込み、都市部の丼、福岡の「ごま鯖」
鯖飯のかたちは地域環境と食文化に応じて三つの代表型に分かれます。すなわち、和歌山の炊き込みご飯、都市部で発達した丼(ひつまぶし式を含む)、そして福岡の「ごま鯖」(刺身和え)です。各地の気候・流通条件が調理法を方向づけた好例といえます。
和歌山:塩鯖の炊き込みご飯(郷土の“おもてなし飯”)

海から遠い山間部の那賀地方では、入手しやすい塩鯖を米とともに炊く素朴な鯖飯が、祭礼や季節の集まりのごちそうとして受け継がれてきました。近年は生鯖に香味野菜を合わせるなど味の洗練も見られます。
※「鯖×米」の保存系譜としては、若狭や京都に伝わるさばずし/焼き鯖すしも広く知られます(同系素材だが寿司文化の系統)。
都市部:丼スタイルと“ひつまぶし式”の食べ方

東京・水道橋の「さばめしの鯖匠」は、丼をそのまま→薬味→出汁茶漬けで楽しむ三段階(ひつまぶし流)を提案し、骨なし加工×鯛出汁などで食べやすさを高めています。
大阪・天満橋の「鯖めし さば七」は国産真鯖にこだわり、カルボナーラ風などの創作系で差別化。
荻窪の「リョウテにサバ」は豊富なトッピングで丼の自由度を広げ、駅近で利用しやすいのが特徴です。
なお丼文化の浸透はコンビニ商品にも及び、ファミリーマートの「さばほぐしごはん」のような身近な選択肢も見られます。
福岡:「ごま鯖」を飯にのせる“生”の系譜
玄界灘に面し鮮度の良い鯖が得られる地理的優位を背景に、福岡では刺身の鯖を甘い九州醤油ベースの胡麻ダレで和える「ごま鯖」が発達。ご飯にのせて食べるスタイルが人気で、塩・焼き中心の地域とは対照的な“非加熱×和え”の系譜を形成しています。
まとめ
・和歌山=保存性と“おもてなし”文化に根差す炊き込み。
・都市部=専門店が牽引する丼(三段階のひつまぶし式)、コンビニにも波及。
・福岡=鮮度優位を活かした「ごま鯖」を飯にのせて楽しむ“生”の系譜。
鯖飯の特徴 – 素材・味つけ・調理法(炊き込み/混ぜご飯/丼・出汁茶漬け)
素材の基本
鯖飯の中心素材は塩鯖または生鯖。和歌山の郷土料理としては、もともと塩鯖を米とともに炊く素朴な型が古典で、現代は生鯖+香味野菜(ごぼう・生姜・生椎茸など)を合わせて風味を高めるレシピも普及しています。仕上げに青ねぎを散らすのが定番です。
味つけの考え方
味つけは醤油・酒・みりん・塩などの和の基本調味を軸に、鯖の脂と出汁の旨味を米に移すのが狙いです。郷土の原型は塩鯖×醤油だけという最小構成で、素材の風味を活かす方向です。
調理法の全体像
鯖飯は大きく炊き込み/混ぜご飯/丼(→出汁茶漬け)の三系統。いずれも「鯖の旨味を米で受け止める」設計で、調理・提供スタイルが異なります。
A. 炊き込み(郷土の基本形)

- 器具:炊飯器/土鍋のいずれでも可。家庭では炊飯器が主流で、現代レシピは時短化・簡便化が進んでいます。
- 流れ:といだ米に調味と出汁を合わせ、鯖(塩鯖または下処理した生鯖)をのせて炊き上げ、蒸らし後に身をほぐして全体に混ぜる。骨は炊く時点では残す/提供前に外すなど家庭差あり(骨を取り除いた“骨なし”加工は外食で普及)。
- 具材:ごぼう・生姜・生椎茸などの香味野菜で香りとコクを補強、青ねぎ・白ごまで香りと彩りを添える。
B. 混ぜご飯(家庭の汎用形)
- 考え方:焼いた鯖の身を炊き立てご飯に混ぜ込む方式。炊飯器の同時調理が不要で、味の濃さや具材(生姜、薬味、梅など)を後入れで調整しやすいのが利点。
C. 丼→出汁茶漬け(現代の外食スタイル)

- 丼:ふっくら炊いた白飯に香ばしい焼き鯖をのせる。都市部の専門店ではそのまま→薬味→出汁茶漬けの三段階(ひつまぶし流)を提案し、食べ進めながら味変を楽しませます。
- 出汁茶漬け:最後は熱い出汁をかけてさらりと。焼きの香りと出汁の相乗で、炊き込みとは異なる“後から重ねる旨味”が核。
地域・家庭で揺れる「濃さ」と「具」
同じ鯖飯でも、塩分の強弱や具材の足し引き(香味野菜の量、薬味の種類、白ごま・青ねぎの有無など)は土地柄や家風で大きく変わります。保存食の名残を引く素朴型から香味を効かせた現代型まで、振れ幅の広さが“鯖×米”文化の魅力です。
基本レシピ(炊飯器・土鍋)と簡単レシピ(混ぜるだけ・缶詰活用)
A. 基本レシピ|炊飯器(2合・目安)

材料
米2合/塩鯖半身(または生鯖)/ごぼう1/2本/生椎茸2~3枚/生姜1片/出汁350~380ml/しょうゆ大さじ1/みりん大さじ2/酒大さじ2/仕上げ用の青ねぎ・白ごま適量
手順
- 鯖は両面を香ばしく焼く。ごぼうはささがき、椎茸は薄切り、生姜は千切りにする。
- といだ米に出汁・調味料を入れ、香味野菜を広げ、その上に焼いた鯖をのせて炊く。
- 炊き上がったら蒸らし、骨を取り除いて身をほぐし、全体をさっくり混ぜる。青ねぎと白ごまを散らして仕上げる。
B. 基本レシピ|土鍋(概要)
米と調味は上記と同様。土鍋に米・出汁・調味を入れ、鯖と具をのせて中火で加熱。沸いたら弱火に落として炊き、火を止めて蒸らす。骨を外してほぐし、薬味を散らす。
C. 簡単レシピ①|混ぜるだけ(焼き鯖 or さば缶)

炊き立てご飯に、焼き鯖のほぐし身やさば水煮缶を加えて混ぜるだけ。生姜、青じそ、白ごま、刻み海苔などを後入れで調整でき、手早く失敗が少ない。
D. 簡単レシピ②|さば缶“汁ごと”炊き込み

さば水煮缶を汁ごと使って炊飯。米2合なら、缶汁と調味を含めて水加減をやや少なめにするとべたつきを防げる。炊き上がりに大葉やねぎを散らすと香りが立つ。
失敗しにくいコツ
- 水加減:出汁や缶汁を使う場合は、その分だけ水を少し控えめに。
- 骨の扱い:炊くと身離れがよくなるので、蒸らし後に骨を外してほぐすと食べやすい。
- 薬味:青ねぎ・生姜・白ごまは“混ぜ込み”でも“仕上げ散らし”でもOK。香り重視なら仕上げ散らしがおすすめ。
食べ方と献立例――汁物・副菜の組み合わせ/お茶漬けアレンジ
基本のいただき方

炊き立ての鯖飯は、だしの香りを邪魔しないやさしい脇役を合わせると全体がまとまります。器は口の広い飯碗にふんわりよそい、青ねぎや白ごまを軽く散らして香りを立たせます。
汁物の相性

- 味噌汁:豆腐×わかめ、里芋×ねぎ、大根×油揚げなど、塩分はやや控えめに。
- 澄まし汁(すまし):三つ葉、えのき、椎茸、かまぼこ等の淡い椀だねで上品に。
- 季節椀:春は若竹、夏はじゅんさい、秋はしめじ、冬は蕪など、季節の一品を添えると格上げ。
副菜の定番

- 漬物:たくあん、浅漬け、梅干し。脂のある鯖の後味をさっぱり整えます。
- 青菜のおひたし:ほうれん草や小松菜におろし生姜少々。
- 小鉢:ひじき煮、切干大根、卯の花、きんぴらごぼう、冷奴。
- 玉子料理:だし巻き卵は子ども受けもよく、献立の彩りに◎。
お茶漬けアレンジ
炊き込みの鯖飯を茶碗に軽く盛り、熱いだし(かつお昆布・いりこ等)またはお茶(ほうじ茶・玄米茶・煎茶)を注いでさらりと。仕上げに刻みねぎ・刻み海苔・山椒を少々。好みでわさび・柚子皮・白ごまを足せば香り高く、体調が優れない時や季節の変わり目にも食べやすい一椀になります。夏場は熱々のだしを少なめにして、湯冷まし~温度控えめでいただくのもおすすめ。
シーン別・献立例
- 平日の定番:鯖飯/豆腐とわかめの味噌汁/青菜おひたし/たくあん
- 来客・行事:鯖飯/澄まし汁(椎茸・三つ葉)/だし巻き卵/ひじき煮/香の物
- 軽めの昼:鯖飯のお茶漬け/浅漬け/冷奴
- 子ども向け(給食風):鯖飯/じゃがいもと玉ねぎの味噌汁/卯の花/みかん
仕上げのコツ
- 味の重ね方:薬味は“のせすぎない”。まずは基本の香り(ねぎ・ごま)から、途中で山椒やわさびで味変を。
- 温度管理:お茶漬けは飯は熱々、だしは熱すぎないが食べやすい。
- よそい方:鯖の身の“ほぐし粗さ”を残すと、口に入るたびに香ばしさが立ちます。
地域の祭礼や学校給食でも親しまれる鯖飯は、素朴な一汁一菜からお茶漬けの締めまで、幅広い場面で活躍します。
現代の展開――専門店文化(東京・大阪・荻窪)とテイクアウト
都市圏で育つ「丼×三段活用」のスタイル

東京・大阪・荻窪などの都市圏では、鯖飯を丼(さばめし丼)として提供する専門店が増え、
- まずはそのまま、
- 薬味(ねぎ・山椒・柚子皮・白ごま 等)で味変、
- 仕上げに熱い出汁をかけて“だし茶漬け”、
というひつまぶし風の三段活用が定番になっています。炊き込み型(郷土の原型)に対し、丼型は焼きの香ばしさ→薬味の清涼感→出汁のやさしさと、味のレイヤーを段階的に楽しめるのが魅力です。
専門店の工夫ポイント
- 骨取り・下処理:小骨をていねいに抜き、臭みを抑える下処理で“食べやすさ”を徹底。
- 火入れと香り:炭火・網焼き・グリルなどで表面は香ばしく、中はふっくら。皮目の脂を活かす焼きが要。
- 米と出汁:米はやや固めに炊き、鯛や昆布・鰹の出汁を合わせるなど、最後の茶漬けでバランスが崩れない設計。
- トッピングの多様化:温玉、柚子胡椒、刻みわさび、しば漬け、青じそ、胡麻だれ…と和の香味を中心に、現代的アレンジも広がっています。
テイクアウト/デリバリーでの最適化
都市部では丼弁当のテイクアウトやデリバリーも一般化。おいしさを保つための工夫がされています。
- 出汁は別添え:カップやポーションで提供し、食べる直前に注いで香り立ちをキープ。
- 薬味は小袋:ねぎ・海苔・山椒・胡麻は“直前トッピング”で食感と香りを守る。
- ご飯の水分調整:冷めてもべたつかないよう、やや固め炊きや油分・塩分の設計を最適化。
- レンジ対応容器:温め直しに耐える容器や、蒸気弁つきフタでふっくら再加熱。
家庭で「専門店風」を再現するヒント
- 焼き分け:皮目を先にしっかり焼いて香りを出し、身側は短時間でふっくら。
- 二段仕込み:丼の素(鯖+たれ)と別添え出汁を用意し、食卓で三段活用を実演。
- 薬味三種:ねぎ+柚子皮(またはレモン皮)+山椒(または七味)を基本セットに。
- ご飯はやや固め:最後の茶漬けでちょうど良くなる硬さに炊く。
コンビニ・通販・お土産――身近に広がる鯖飯
コンビニで手軽に
近年はコンビニ各社が「さば系ごはん」を定期的に展開。たとえばセブン‐イレブンでは炙り焼きさば御飯など、焼いた鯖を盛り付けたご飯商品が地域限定で登場します(取扱い・時期は地域により変動)。
ファミリーマートは直巻 塩さばなど“さば系おむすび”を販売。さらに、弁当用の塩サバ切り身の端材を活用した「直巻 焼さば」を発売するなど、サステナブルな取り組みも進んでいます。
通販で「さばフレーク」を常備
自宅で鯖飯アレンジを楽しむなら、焼き鯖フレークやさばほぐしを常備すると便利。久世福商店の「ゴロゴロほぐし焼鯖」のように、ご飯のお供・おにぎり・お茶漬けに使える瓶詰も人気です。
お土産で“伝統の系譜”に触れる
和歌山のなれずし(早なれ/中なれ/本なれ)は、鯖と米文化の“保存系”を体感できるお土産。県内店舗やオンラインでも入手可能で、地域に根づく味を持ち帰れます。
使い方アイデア
- コンビニの“さばごはん”をベースに刻みねぎ・山椒を足して一段リッチに。
- さばフレーク+温かいご飯で即席混ぜご飯→最後は出汁をかけてお茶漬けに。
- 旅の土産の“なれずし”はスライスして少量をご飯と。保存系の酸味と旨味を楽しめます。
保存・弁当術――冷凍・持ち運びのコツ
冷蔵保存(当日~翌日まで)
- 粗熱取り:炊き上がりはバットに広げて急冷(うちわ・扇風機・保冷剤を下に敷く等)。深い容器のまま放置はNG。
- 保存容器:清潔な浅型容器に入れ、フタをずらして完全に冷ましてから密閉。
- 目安:冷蔵で1日(翌日まで)を推奨。夏場や高温時は当日中が安心。
- 再加熱:食べる直前に中までアツアツになるまで温める(電子レンジはラップ+少量の水を振るとふっくら)。
冷凍保存(作り置きに最適)

- 下ごしらえ:骨や皮の硬い部分は除く(解凍後の食感対策)。青ねぎなど生の薬味は別添えに。
- 小分け:1食分ずつ平らに薄く(約1~2cm厚)してラップ→フリーザーバッグ。日付ラベル必須。
- 目安:2~3週間で食べ切る。
- 解凍・温め:電子レンジで半解凍→ほぐして再加熱がムラなく仕上がる。仕上げにだし少量を回しかけると香り復活。
- 風味アップ:解凍後に追い生姜・追いごま・刻みねぎを添えると作りたて感が戻る。
弁当に持っていく(夏・行事・通勤)

- 朝に炊く or 前夜仕込み:前夜の場合は完全に冷やしてから冷蔵→翌朝再加熱し、再び冷ましてから詰める。
- 詰め方:弁当箱は完全に冷えた中身を詰める(湯気が残ると結露→傷みの原因)。上面は薄く平らにして冷めやすく。
- 保冷:保冷剤+保冷バッグは夏の必須装備。直射日光を避ける。
- 相性の良いおかず:高水分・生野菜は避け、出汁巻き・ひじき煮・きんぴら・浅漬けを水気切りで。
- “お茶漬け弁当”応用:小さなボトルに濃いめのだしを持参。昼に温めた鯖飯へ注いでだし茶漬けでさっぱり。
おにぎり化する


- 握り方:やや固めに握り、表面に白ごま。のりは別包にして食べる直前に巻く。
- 冷凍おにぎり:握ったら急冷→個包装→フリーザーバッグ。解凍はラップのままレンジ。中心が温まったら一度ほぐし、再度温めるとムラが減る。
よくある失敗と対策
- べたつく:炊く段階で水分過多。冷凍時は薄く平らにして急冷、温め直し時は少量のだしで調整。
- 魚の臭い:生姜・酒を下味に、焼き目をしっかり。保存は密閉+二重包装。
- パサつき:温め直しの前に霧吹きや手水、ラップで蒸し戻し。
- 色がくすむ:青ねぎ・海苔は後がけ。混ぜ込むと変色・水分移行で劣化しやすい。
- 骨が気になる:炊く前に大骨は除去、小骨は蒸らし後に丁寧に除く。
おすすめ“作り置きパック”
- ベース鯖飯(具はごぼう・椎茸・生姜のみ)を小分け冷凍。
- 薬味ミックス(刻みねぎ+炒りごま+柚子皮少量)を別保管。
- 食べる際に薬味を後のせ/締めはだし茶漬けの二段構えで、作り置き感が出ない。
英語で紹介する鯖飯(Mackerel Rice / Rice cooked with mackerel)
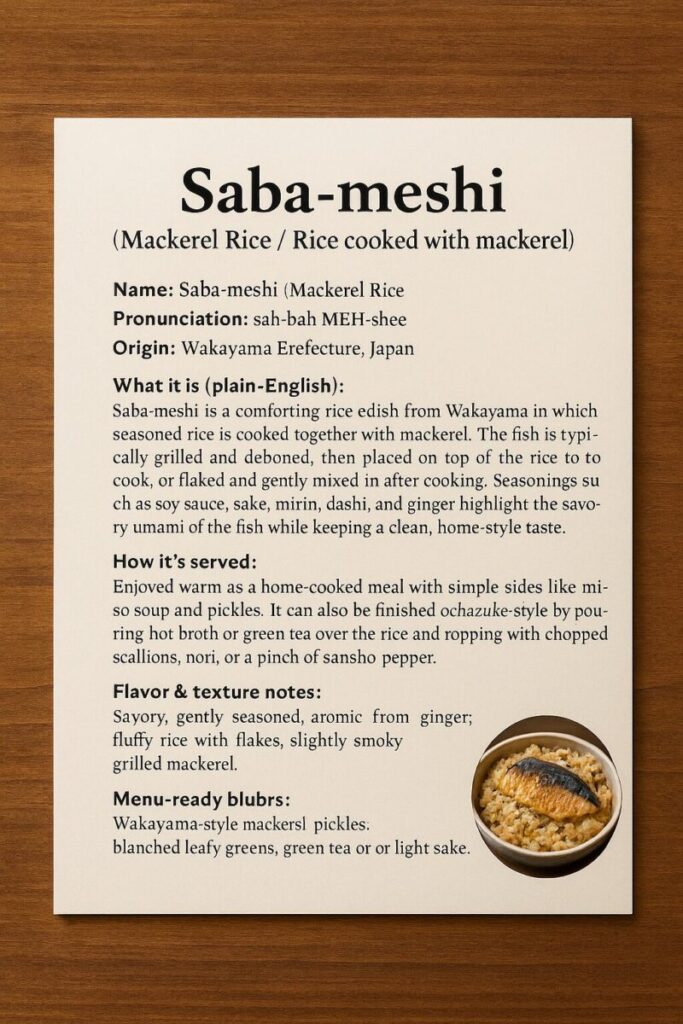
Name: Saba-meshi (Mackerel Rice / Rice cooked with mackerel)
Pronunciation: sah-bah MEH-shee
Origin: Wakayama Prefecture, Japan
What it is (plain-English):
Saba-meshi is a comforting rice dish from Wakayama in which seasoned rice is cooked together with mackerel. The fish is typically grilled and deboned, then placed on top of the rice to cook, or flaked and gently mixed in after cooking. Seasonings such as soy sauce, sake, mirin, dashi, and ginger highlight the savory umami of the fish while keeping a clean, home-style taste.
How it’s served:
Enjoyed warm as a home-cooked meal with simple sides like miso soup and pickles. It can also be finished ochazuke-style by pouring hot broth or green tea over the rice and topping with chopped scallions, nori, or a pinch of sansho pepper.
What it’s not (to avoid confusion):
Saba-meshi is not fermented mackerel sushi (narezushi). While both celebrate mackerel, saba-meshi is a cooked rice dish; narezushi is a preserved/fermented sushi tradition.
Flavor & texture notes:
Savory, gently seasoned, aromatic from ginger; fluffy rice with flakes of tender, slightly smoky grilled mackerel.
Menu-ready blurbs (choose one):
- Long (about 40–50 words):
Saba-meshi is Wakayama’s traditional mackerel rice—seasoned rice cooked with grilled, deboned mackerel, gently flavored with soy sauce, sake, mirin, dashi, and ginger. Served warm with simple sides, or as ochazuke with hot broth or tea. A comforting taste of coastal Wakayama. - Short (about 20 words):
Wakayama-style mackerel rice: seasoned rice cooked with grilled mackerel, soy, mirin, and ginger. Also great as ochazuke with broth. - Label (≤10 words):
Wakayama mackerel rice, gently seasoned and aromatic.
Allergen / dietary note (for menus):
Contains fish (mackerel) and soy; soy sauce may contain gluten.
Pairing ideas:
Miso soup, light clear soup, pickles, blanched leafy greens; green tea or light sake.
参考文献・参照資料
日本語資料
- 和歌山県「鯖めし(郷土料理)」(PDF)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/nousin/naganoaji_d/fil/sabamesi.pdf - 郷土料理ものがたり「鯖めし」
http://kyoudo-ryouri.com/ja/food/636.html - 全国学校栄養士協議会「和歌山の郷土料理・鯖めし」
https://www.zengakuei.or.jp/gyoji/wakayama_3.html - EATS.jp「鯖めし(和歌山県)」
https://eats.jp/detail/100774&rut=728e8fc49c111aca80a214714d9546f711d793f89f622d281333d201bfcb1285 - note「鯖めしの作り方(家庭料理の実践例)」
https://note.com/as_cooking/n/n76c7cab2ec43 - Mainichi Grill部「鯖めしレシピ」
https://www.mainichigrillbu.com/recipe/2340 - 春日部市立(学校配布資料)郷土料理・鯖めし(PDF)
https://schit.net/kasukabe/esushijima/cabinets/cabinet_files/download/82/2553ba1c3ee93eb608b7650f362766d7?frame_id=143 - べったんさん「早なれ寿司」(保存食文化の関連資料)
https://www.bettinsan.jp/%E6%97%A9%E3%81%AA%E3%82%8C%E5%AF%BF%E5%8F%B8/ - セブン‐イレブン 商品情報(炙り焼きさば御飯 ほか)
https://www.sej.co.jp/products/a/cat/010020010000000/ - ファミリーマート 商品情報(おむすび/弁当カテゴリ)
https://www.family.co.jp/goods/omusubi.html
https://www.family.co.jp/goods/obento.html - 久世福商店「ゴロゴロほぐし焼鯖」
https://kuzefuku.com/?page_id=13&eci_product=fsh01951 - SABAR(サバー)公式サイト(鯖加工品・惣菜の参考)
https://sabar38.com/ - Green Hill ホテルコラム「和歌山の名物料理」
https://hotel-greenhill.jp/articles/column06/ - Yahoo!ニュース(エキスパート寄稿:さば関連トピック)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cb6510905b66b4584ae0356e15d80d88851f6bc4 - 味いち遥か・和み オンラインショップ(鯖飯関連商品)
https://shop.ajiichiharuka-nagomi.com/items/75804423
英語資料
- MAFF(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
“Regional Cuisine—Wakayama (Saba-meshi / Mackerel Rice)”
https://www.maff.go.jp/e/policies/market/k_ryouri/search_menu/2702/index.html - JapanTravel “Regional Cuisine: Wakayama”
https://en.japantravel.com/guide/regional-cuisine-wakayama/62894 - Wakayama Hidaka History & Culture—“Washoku in Wakayama”(英語パンフレット・PDF)
https://wakayama-hidaka-history.jp/introduce/washoku_eng/pamph_sp.pdf - Wakayama Prefecture—“Wa no Shokutaku”(英語版・PDF)
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071700/an_nai/d00213509_d/fil/wanoshokutakuEnglish.pdf - EATS.jp (EN) “Saba-meshi (Mackerel Rice)”
https://eats.jp/en/detail/100774&rut=15e587b4838de7a89629545a214e6eb2a55ac0b50af6cd0ab19efb3d4f4063ae - CNN Travel “Wakayama: foods to try”
https://www.cnn.com/travel/article/wakayama-japan-foods - Hotels.com “Best local dishes from Shirahama, Wakayama”
https://www.hotels.com/go/japan/jp-best-local-dishes-from-shirahama
※ 本一覧は、郷土料理としての位置づけ・歴史背景・家庭調理・外食・中食(コンビニ)・関連保存食(なれ寿司)・英語紹介の各節で参照した主な資料です。

コメント